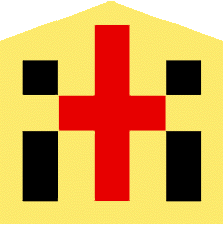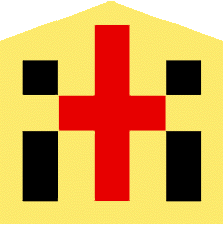|
上のグラフがドラム式での焙煎開始から終了までの温度変化を示した焙煎プロファイルです。
ドラム式では、豆の投入前に釜の中の温度を予め200℃程度に暖めてから豆を釜に投入します。室温の豆が大量に投入されると豆は大量の熱を熱風から奪います。このため、温度は200℃から100℃以下に急降下します。
このグラフから2つの事が判ります。グラフ上の温度は豆の温度ではなく、釜の中の空気の温度である事。ドラム内の温度と豆表面温度は200℃の高温に達すると言う点です。
先にも記しましたが、熱の伝わり方には伝導・対流・放射という3つがあります。伝導は隣り合う物体を経由して熱が順次伝わります。対流は気体や液体のような流体が熱を運びます。伝導と対流では熱は高温から低温へと広がっていきます。温度差が無いと熱の移動は生じません。放射は電磁波が熱を伝えます。遠赤外線は電磁波の一つです。
ドラム式では上記の対流、つまり空気を加熱し、熱風で豆の表面を加熱し、豆の芯は伝導熱によって加熱されます。
豆の表面温度は比較的早く熱風温度と同じになります。同じになると熱風から豆への熱移動が無くなり、豆表面から芯部への熱流も無くなります。その結果、豆の表面は焦げても芯部は生のままになります。つまり煎り斑が生じます。熱風式焙煎の豆に、私にはトゲが有る様に感じられ、後味にも尖った刺激を感じるのはこのためだと思われます。
豆の内部への熱量を増やすには豆の表面温度を、引いては空気の温度を更に高くしなければなりません。これが空気温度を200℃近くの高温にする理由であり、熱風式での温度制御に経験が必要なのもこのためです。
遠赤外線は物体が加熱されるとその表面から放出され、真空・空気を透過し、物体に当たると、遠赤外線が持つエネルギーで物体内の分子が共振を起こし、その振動で摩擦熱が生じます。放出された遠赤外線量に比例した熱量が豆の芯に向かって移動します。
さて、珈琲の生豆は30〜40μm程度の独特のほぼ均質な細胞(内乳細胞)で構成されていますが、一つ一つの細胞を取り囲んでいる細胞壁が異様に厚く、ヘミセルロースという成分を非常に多く含んでいる(コーヒーの科学 旦部幸博著)そうです。
発熱反応中に豆の細胞内の成分は膨張し,膨張圧が大きくなるとその成分を包んでいた細胞壁が破れ中のガスが外に噴出します。この噴出は2度起こります。1ハゼと2ハゼです。珈琲の味と香りはこれらの細胞壁に吸着されたり、ガスとして空胞に閉じ込められます。
焙煎完了時には水分、CO2、揮発性成分が無くなるので質量は25%減少し、体積は豆が膨らみスポンジ化するので約1.5倍程度大きくなります。
豆の温度が195℃に達しないとアロマが未発達になり、渋く青臭い味になり、逆に235℃を越えるとアロマは焼抜けて焦げ臭い味が生まれます。(詳しくは旦部幸博著「コーヒーの科学」を参照下さい。)(注意:文195℃や235℃の温度は熱風式での温度であって、焙烙使用時の温度ではありません。松田)
|